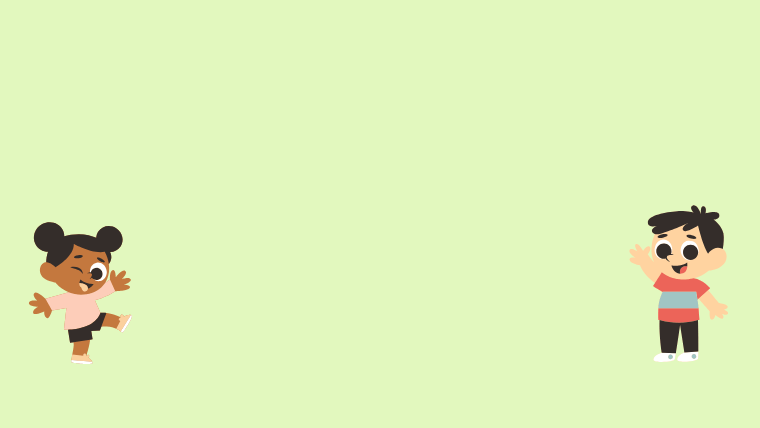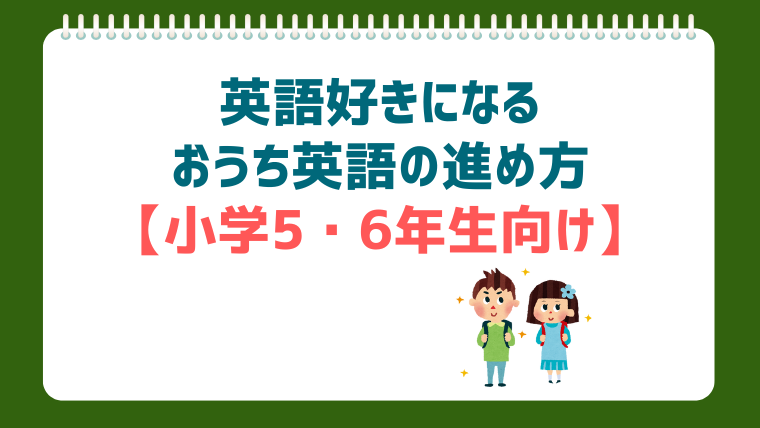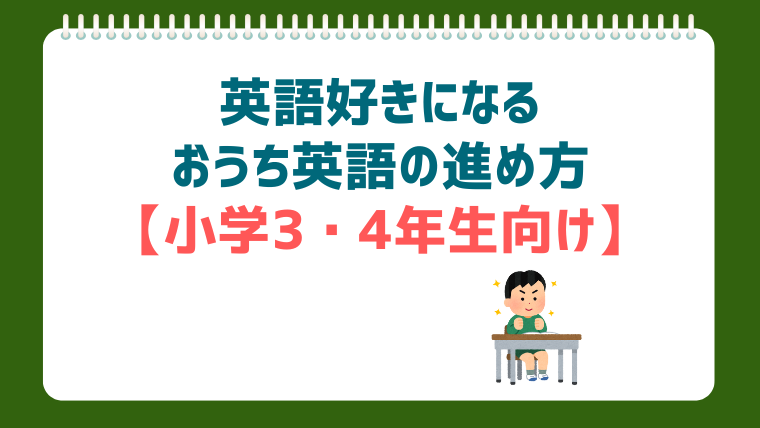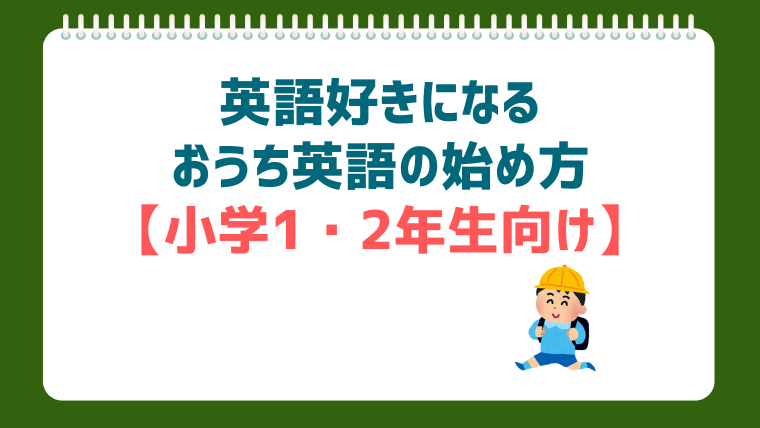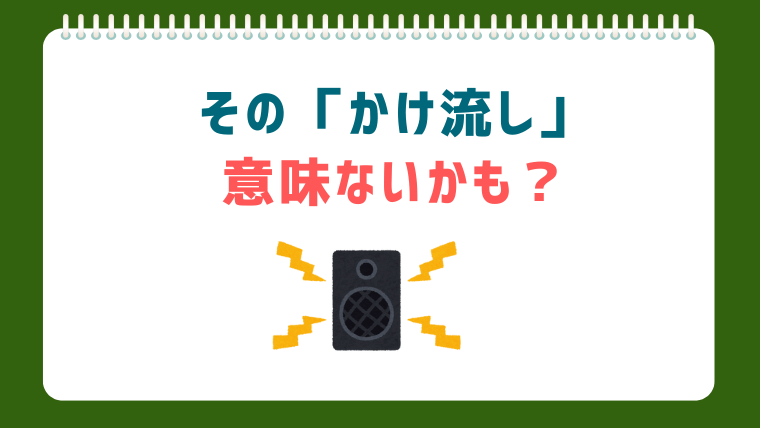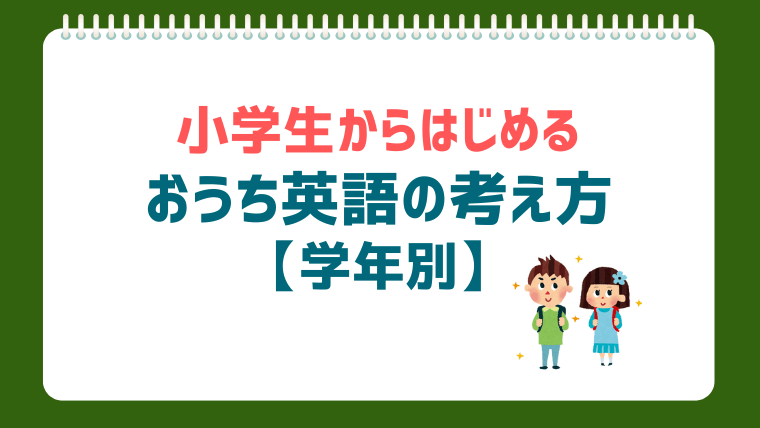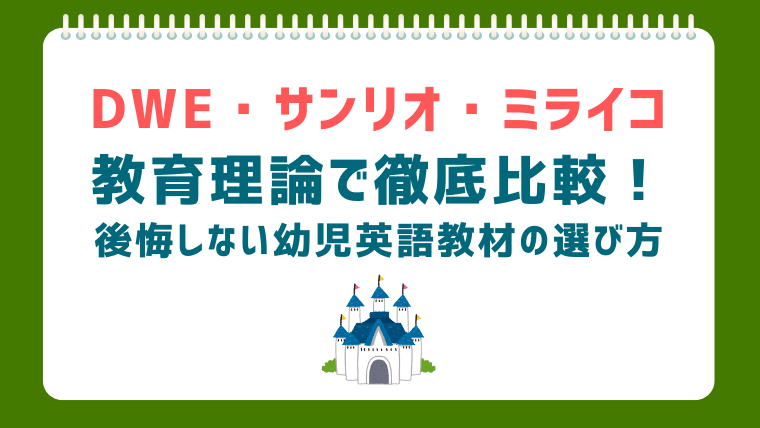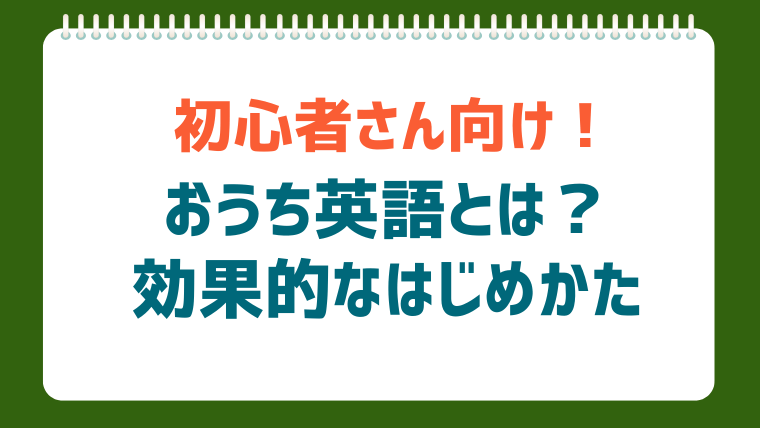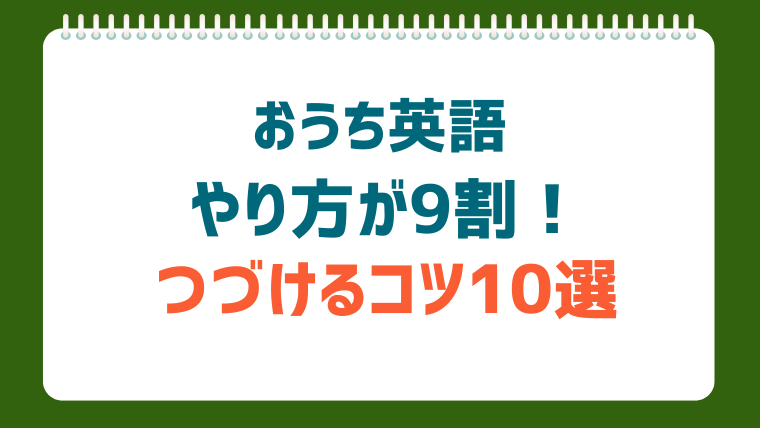おうち英語で後悔する前に|よくある失敗パターン7選と体験談
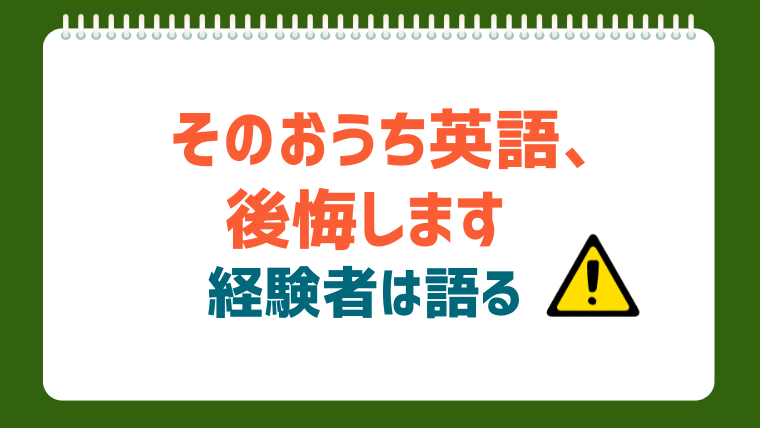
こんにちは。元翻訳者(英検1級)、子育て卒業組の「ねこみみ」です
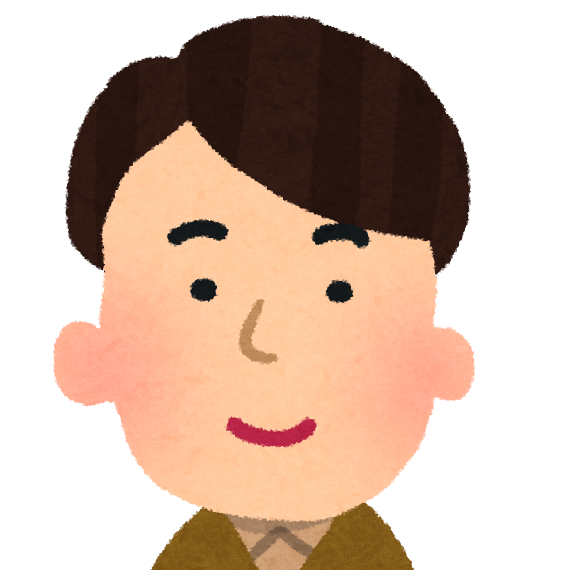
我が子には、英語で苦労してほしくない
そんな想いから始まる「おうち英語」
子どもの可能性を広げられる素晴らしい取り組みとして、多くのご家庭が実践されています
しかし、その道のりの途中や、お子さんが成長しておうち英語卒業を迎えた頃に、「もっとこうすれば良かった…」と感じる共通の課題が存在することも事実
この記事では、わたしの体験談にとどまらず、多くの「おうち英語」経験者が直面しがちな後悔のパターンを7つ、客観的に解説します
記事の最後には、私自身が「こうしておけばよかった…」と感じた失敗談も、正直にお話ししますね
今まさに取り組んでいるあなたの現在地を確認し、未来へのヒントを見つけるきっかけになればうれしいです
- おうち英語で経験者が陥りがちな後悔のパターン7つ
- 筆者が特に後悔している具体的な体験談
- これから「おうち英語」を始めようと考えている人
- 現在「おうち英語」に取り組んでいて、やり方に迷いや不安がある人
「おうち英語」直面しがちな後悔パターン7つ
【視点1】保護者の「気持ち」に関する落とし穴
家庭での教育は、保護者の心理状態が子どもの学習意欲に直結します
良かれと思ったことが、いつの間にかプレッシャーになっていないか、振り返ってみましょう
後悔パターン1:完璧な「バイリンガル」という幻
SNSなどで目にする流暢な子どもたちの姿に、「我が子もあのように」と高い理想を掲げてしまうのは自然なことです
しかし、その理想が完璧を求める気持ちに繋がり、英語を話すこと自体にプレッシャーを与えたりするケースが見られます
英語が「親の成果」になった瞬間、子どもから自発的な楽しさが失われがちです
後悔パターン2:他者との「比較」が生む焦り
子どもの言語習得のスピードは、一人ひとり全く異なります
特に、十分なインプットを蓄積している「サイレントピリオド」の存在を知らないと、発話が少ない我が子と他の子を比べてしまい、保護者が焦りを感じてしまいます
その焦りは子どもにも伝染し、健やかな成長の妨げになる可能性があります
後悔パターン3:いつの間にか「義務」になる
「毎日1時間はかけ流しを…」「今日はこの絵本を…」といった日々の目標が、いつしか「やらなければならない」という義務感に変わってしまうことがあります
保護者が楽しんでいない活動を、子どもが心から楽しむのは難しいもの
英語の時間が親子にとって「タスク」になってしまうと、学習効率は大きく低下してしまいます
【視点2】「やり方」のバランスに関する落とし穴
どのようなスキルに重点を置くか、そして母語とどう両立させるかは、長期的な成功を左右する重要なポイントです
後悔パターン4:「わかる」だけで「使えない」
大量のインプットにより、リスニング力、いわゆる「英語耳」は非常に良く育ちます
しかし、「わかる(インプット)」と「使える(アウトプット)」は別のスキル
実際に英語でコミュニケーションをとる機会が不足していると、知識はあっても話す自信が育たず、実践的な場面で言葉が出てこないという壁にぶつかります
後悔パターン5:「読み書き」への準備不足
幼児期は「聞く・話す」が中心になりますが、その後の「読む・書く」という文字学習への移行を意識できているかは、大きな分かれ道です
特に、文字と音のルールである「フォニックス」の基礎に遊びながら触れておかないと、小学校での英語学習が始まった途端につまずきの原因となることがあります
後悔パターン6:「国語力」という土台の軽視
英語教育に熱心になるあまり、結果として日本語の絵本の読み聞かせや、思考力を育む対話の時間が減ってしまうことがあります
あらゆる言語能力や思考力の土台は「母語」です
この土台がしっかりしていないと、その上に積み上げる外国語の能力も不安定になりがちです
【視点3】「次のステップ」への移行に関する落とし穴
おうち英語の最大の壁とも言えるのが、学校で始まる「教科としての英語」へのスムーズな移行です
後悔パターン7:「楽しい英語」と「学ぶ英語」の断絶
家庭で育んだ「コミュニケーションツールとしての英語」と、中学校から始まる文法や試験を前提とした「教科としての英語」には、大きなギャップがあります
このギャップを埋める橋渡しがないと、子どもは戸惑い、あれほど好きだったはずの英語に苦手意識を持ってしまう危険性があります
【筆者の告白】「こうすれば良かった」と痛感した2つの後悔
ここまで一般的な後悔のパターンを見てきましたが、ここからは少しだけ、私自身の話をさせてください
ありがたいことに、我が家では楽しむことを大切にできたので、プレッシャーや焦りといった『気持ち』の面での後悔はありませんでした
ですが、だからこそ純粋に『やり方』の部分で、今も『ああすれば…』と振り返ってしまう大きな後悔が2つあります
後悔①:「わかる」だけで、「生きたツール」にできなかった
(元:後悔パターン4:「わかる」だけで「使えない」)
かけ流しや、家庭内での簡単な会話。これらは実践していました
しかし、子どもにとって、親以外の誰かとコミュニケーションをとるための「生きたツール」にはなっていませんでした
今になって痛感するのは、もっと早くから第三者の力を借りるべきだったということ
特にオンライン英会話などを活用し、「親ではない誰かと英語で話す」という経験を積ませてあげていれば、「わかる」から「使える」への壁を、もっと楽しく乗り越えられたはずだと感じています
英検などを受験する予定があれば早くからオンライン英会話で会話に慣れておくことも大切ですね
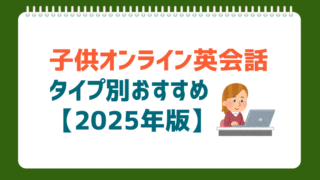
後悔②:フォニックスを後回しにしてしまった
(元:後悔パターン5:「読み書き」への準備不足)
そして、こちらが私の最大の後悔です
フォニックスの重要性は、当時から情報として知っていました
ですが、「どう教えたらいいの?」と、日々の忙しさを言い訳に、本格的に取り組むことを後回しにしてしまったのです
その本当の意味に気づいたのは、子どもがずっと大きくなってから
高校受験レベルの英単語なら、気合と暗記で乗り切れるかもしれません
しかし、大学受験で求められる語彙量は桁違い
フォニックスの本当の価値は、単に発音が綺麗になることではありません
知らない単語でも、文字の組み合わせから『音を推測できる力』が身につくことです
この力が土台となり、
- 推測して発音できる→リーディングのスピードが向上する
- 正しい音を理解できる→リスニングの精度が向上する
という相乗効果が生まれ、結果として、英語学習全体の効率がアップするのです
つまり、限られた時間で戦う受験勉強において、圧倒的な『時短』という武器になる
私はその重要性に後から気づき、大変後悔しました😥
まとめ:後悔のパターンを知り、未来の学びに変える
これらは、誰にでも起こりうる、おうち英語における典型的な課題です
子どもの成長段階や環境の変化に応じて柔軟にやり方を見直していくための「視点」として活用することが大切です
我が家はもうおうち英語は卒業してしまいましたが、この記事が、今がんばっているあなたのご家庭にとって最適のバランスを見つける一助となれば幸いです