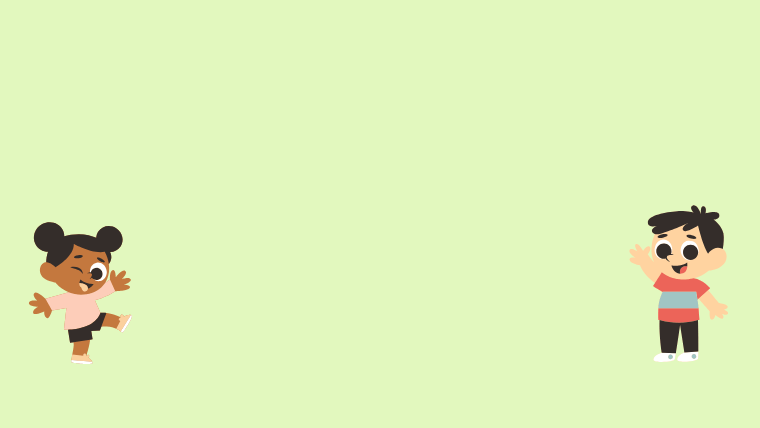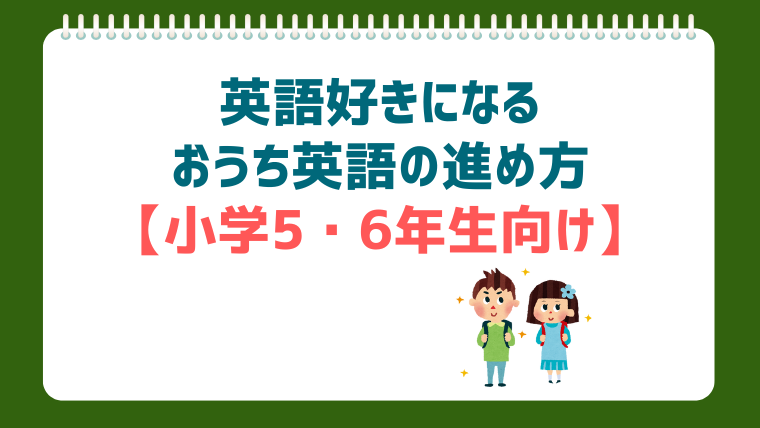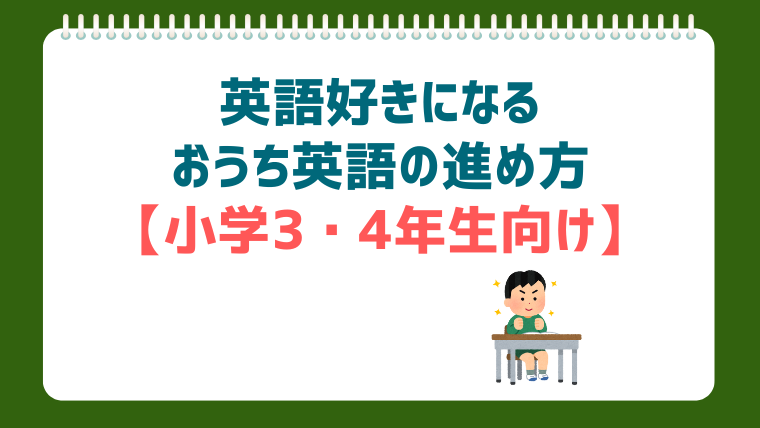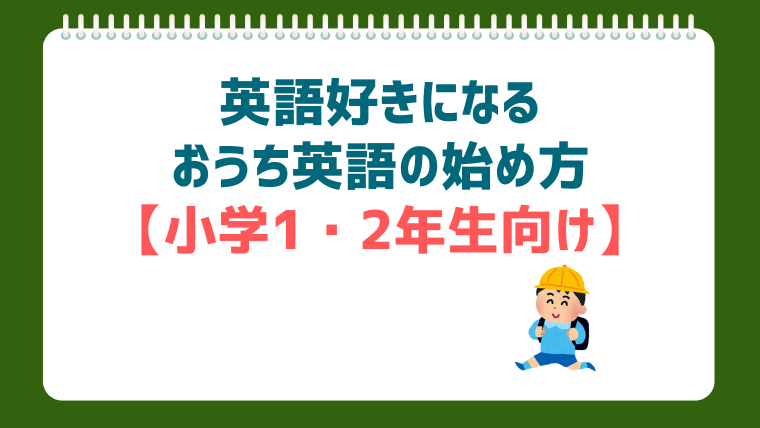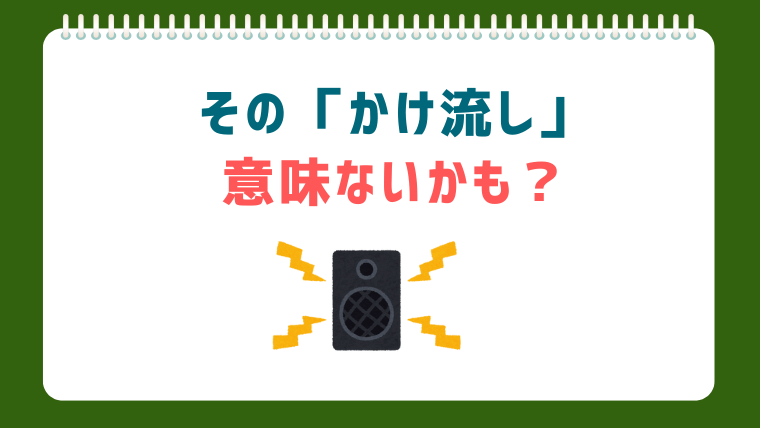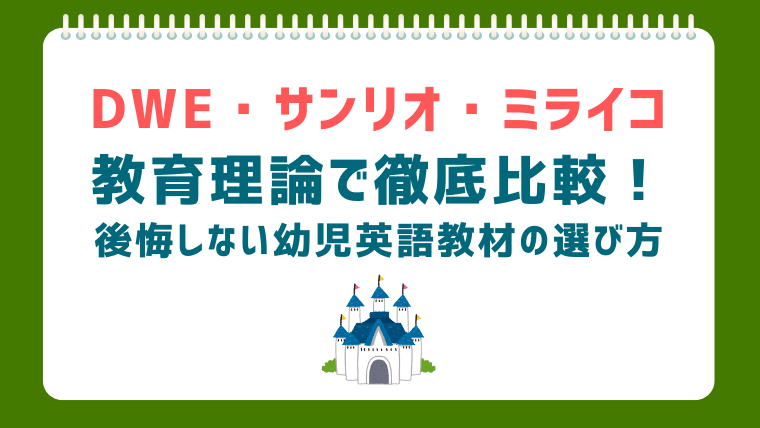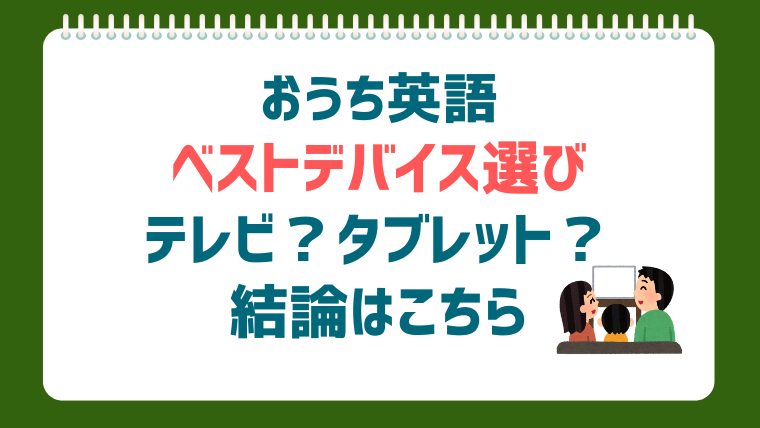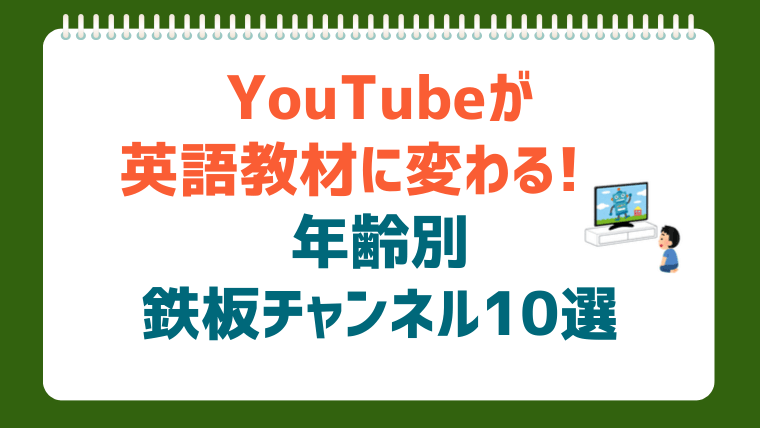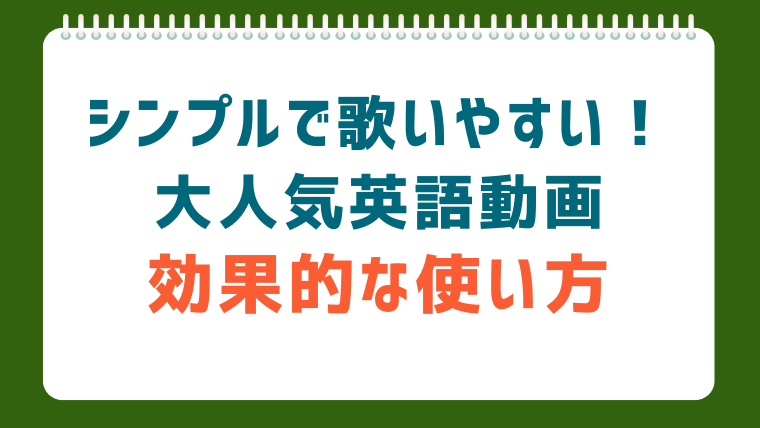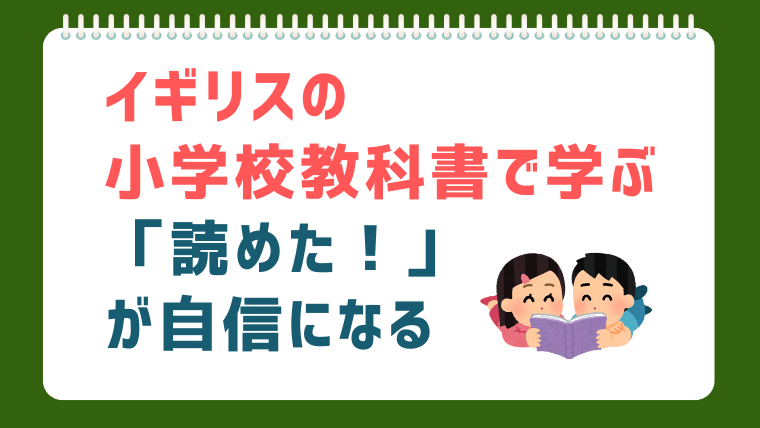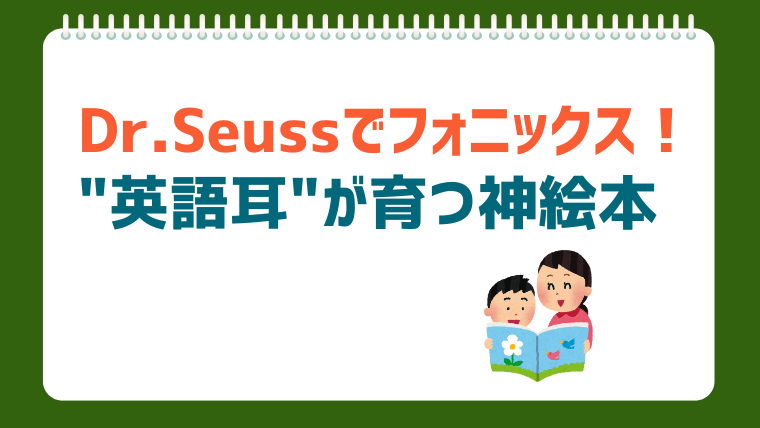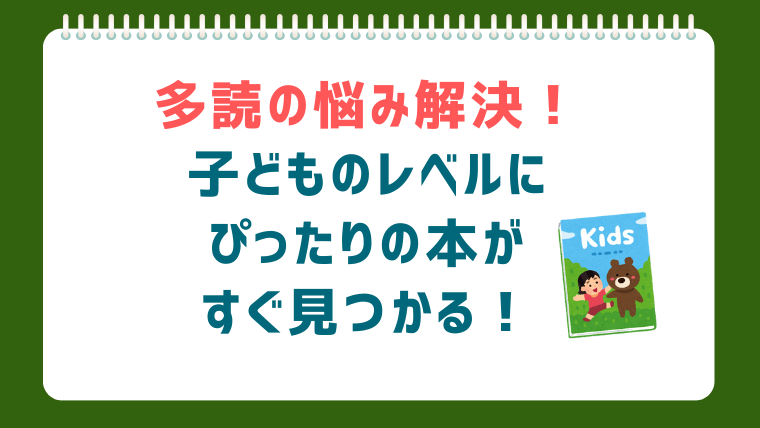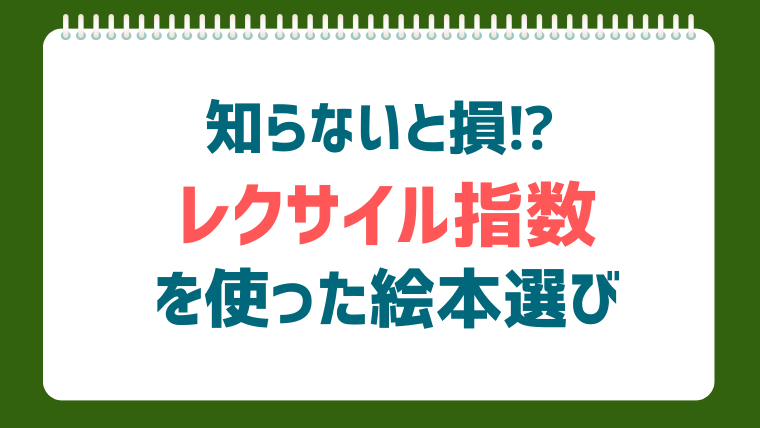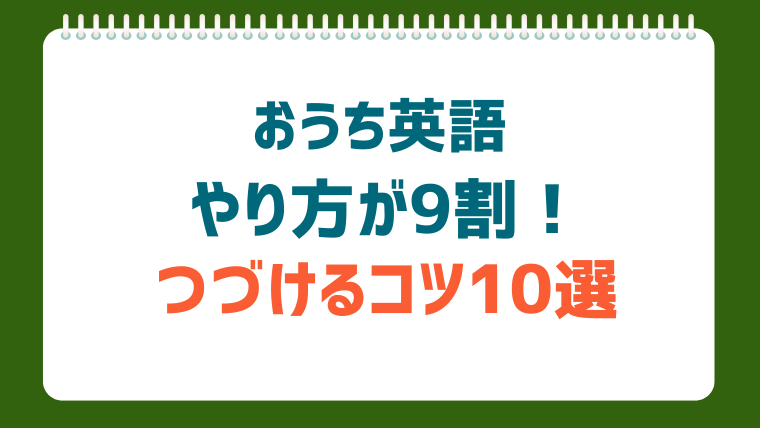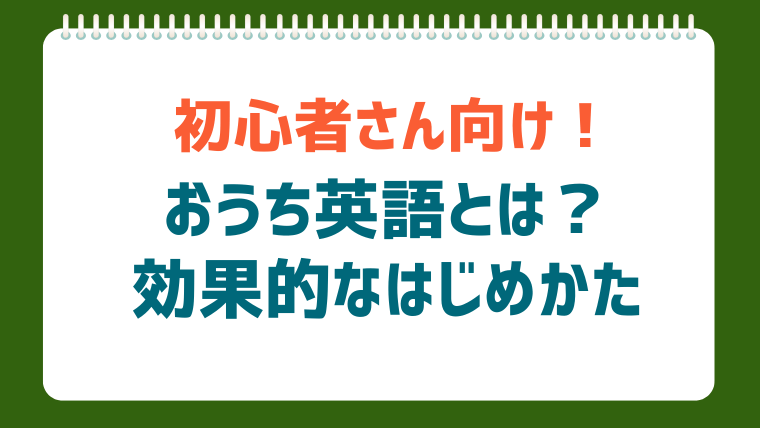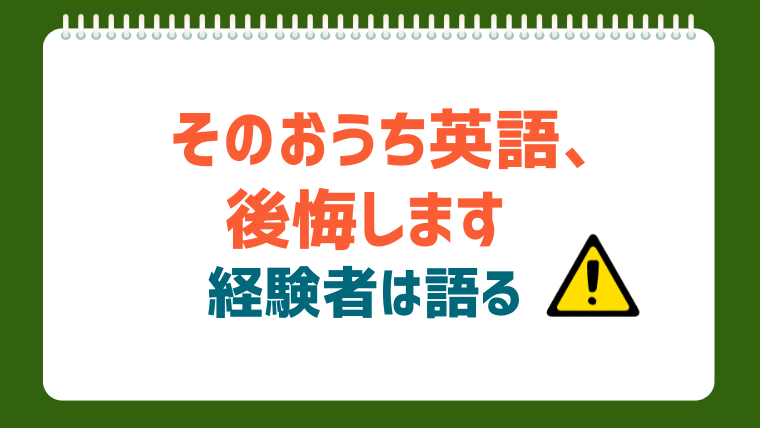脳科学が教える、小学生の英語力を家庭で伸ばす方法【学年別】
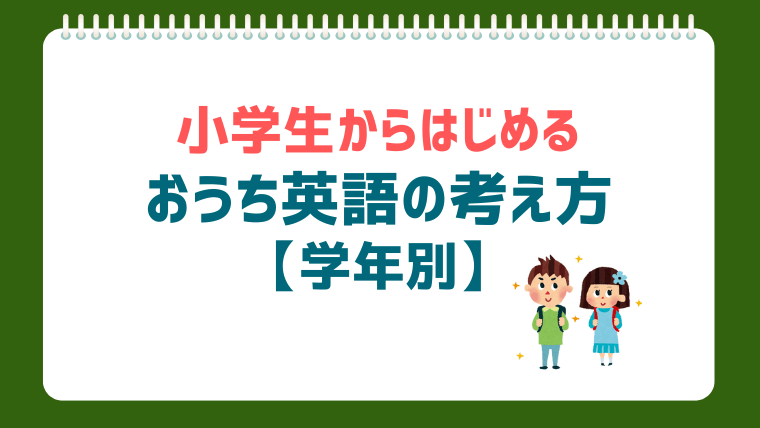
こんにちは。元翻訳者(英検1級)、子育て卒業組の「ねこみみ」です
2020年度から、小学校での英語教育が本格スタートしましたね

今まで英語なんてやってこなかった…
うちの子は大丈夫?
と、不安に感じている保護者の方も多いのではないでしょうか
そこで本記事では、これまで英語経験のない小学生でも効率的に英語を身につけられる方法を、脳科学・言語学・心理学の知見に基づいて解説します
- 脳科学に基づいた、効果的な言語習得のポイント
- 小学校の新しい英語カリキュラムの概要
- 小学生の学年(低・中・高学年)ごとに最適な英語学習法
- 家庭で子どもの英語学習をサポートする具体的な方法
- 子どもの英語教育に不安や疑問を持つ方
- 子どもの年齢に合った効果的な学習法を知りたい方
- 英語が苦手で、家庭でのサポート方法に悩んでいる方
言語習得を支える科学的しくみ
効果的な学習法を考えるには、子どもがどのように言葉を身につけるかを科学的に理解することが大切です
ことばを育む脳のしくみ
小学生の脳は「神経可塑性」が高く、新しい言語に触れることで神経回路を柔軟に組み替え、脳の構造そのものを変化させる力があります
この時期は「感受性期」と呼ばれ、発音やリズムを身につけやすい特徴があります
- 低学年
耳と脳の柔軟さを活かし、遊びや歌を通じて自然にネイティブに近い音を吸収しやすい時期です - 中学年
聴覚の柔軟性はまだ残るものの、母語フィルターの影響が少しずつ出てきます。フォニックスやチャンク学習を取り入れ、「音と文字」を結びつけながら、リズムや発音を意識的に定着させることが効果的です - 高学年
母語フィルターが強まり自然吸収は難しくなりますが、模倣力や意識的学習力が高まります。発音記号や口の形、音の法則を意識した練習を通して、クリアな発音や自然なリズムを磨くことができます
このように、学年ごとにアプローチを変えることで、どの時期からでも発音力やリズム感を効果的に伸ばすことが可能です
また、よくある心配「早く英語を始めると母語の発達が遅れる」は、科学的には誤りです。バイリンガルの脳は二つの言語を使い分けるため、注意力や問題解決力などの認知能力がむしろ高まることがわかっています

発達段階に合わせた自然な順序で学ぶことが大切だよ
ことばを学ぶ方法:言語学×心理学
言語習得研究の大家、スティーブン・クラッシェンの理論は、効果的な学習法を考えるうえで欠かせません
彼の理論の核心は、言語は意識的に「学ぶ」ものではなく、コミュニケーションを通じて自然に「身につける」ものだという点です
理解できるインプットがカギ
言葉を覚えるには、子どもが理解できる英語(少しだけ難しいレベルの内容)に触れることが大切です。文脈や絵を手がかりに理解しようとすることで、新しい単語や表現が自然に身につきます
不安や緊張は習得のブレーキ
どんなに良質なインプットがあっても、不安や自信のなさといった否定的な感情は、「情意フィルター」と呼ばれる心理的な壁を作り、習得を妨げます
そのため、教育で最も大切なのは、子どもが安心して挑戦できる環境を整えることです。間違いを恐れず、好奇心をもって学べる場こそ、学習意欲を引き出す鍵となります
日本の小学校英語教育:2020年度からの新カリキュラム
2020年度から、小学校の英語教育は大きく変わりました
3・4年生:「外国語活動」
ここでは、テストの点数はつきません。めざすのは「聞く・話す」を中心に、英語の音に慣れ、コミュニケーションの楽しさを体験すること。英語との出会い期です
5・6年生:「外国語(教科)」
高学年になると、いよいよ「読む・書く」が加わり、4技能すべてを学んでいきます。学習内容も系統的になり、成績として数値で評価されるようになります。つまり、ここから本格的な学び期が始まるわけです
この流れは、子どもたちがまず「音声に親しみ → 英語を使ってみる楽しさを知り → 読み書きへと広げる」という自然なステップで進めることを意図しています
2020年小学校英語教育カリキュラムの比較
| 特徴 | 3・4年生(外国語活動) | 5・6年生(外国語) |
| 公式名称 | 外国語活動 | 外国語科 |
| 目標 | 英語に慣れ親しみ、学習への動機付けを高める | コミュニケーションを図る基礎能力を育成する |
| 年間授業時数 | 35時間(週1コマ程度) | 70時間(週2コマ程度) |
| 対象技能 | 主に「聞くこと」「話すこと」 | 「聞く・話す・読む・書く」の4技能 |
| 評価方法 | 記述による評価 | 数値による観点別評価 |
ただし、専門家によると、英語習得には2000〜3000時間のインプットが目安とされます。これは、理解可能な英語に多く触れることが重要だという「インプット仮説」に基づくものです
一方、現在小学校における英語の授業時間は、3・4年生で年間35時間、5・6年生で年間70時間です。6年間を合計しても約210時間にとどまり、中学校、高校の授業時間をすべて合わせても約1000時間程度です

学校だけでは英語に触れる量が足りないため、家庭でのインプットが大切だよ
学年別の効果的な学習戦略
脳の成長と学校教育の仕組みをふまえ、学年ごとに最適な英語学習法をまとめました
小学1~2年生:音と遊びで楽しい土台作り
低学年の目標はとてもシンプル
英語を「勉強」ではなく「遊び」として楽しむことです
この時期は音に敏感なので、学習は徹底して 耳と口を使った体験型 がベスト。文字や文法はまだ必要ありません。
- 歌・チャンツ・リズム遊び
メロディーにのせた言葉は、驚くほど記憶に残ります。リズムと一緒に英語の音や抑揚が自然と身につきます - 絵本の読み聞かせ
絵がヒントを与えてくれるので、知らない単語も「なんとなく理解」できる。これが強力な「理解可能なインプット」になります - TPR(体を動かして学ぶ方法)
“Stand up.” “Clap your hands.” のような指示に体で反応するアクティビティ。話すことを強制しないので、安心して「沈黙期」を過ごせます
この段階では 間違いを訂正しない のが鉄則
「楽しい!」「もっとやりたい!」という気持ちこそが、次のステップにつながる一番の力になります
小学3〜4年生:会話から文字への橋渡し
低学年で築いた「音の土台」をもとに、この時期は 目的のあるやりとり へ発展させます。同時に、いよいよ「音」と「文字」を結びつける大事な移行期に入ります
- フォニックスで音と文字をリンク
アルファベットと音のルールを学ぶことで、自分で単語を読めるように
「読めた!」という体験は大きな自信となり、学習意欲を一気に高めてくれます - チャンク学習で表現の型をインプット
たとえば「I like ~.」のように、意味のある言葉の塊を丸ごと覚える方法です
基本形をそのまま使ったり、一部を入れ替えたりしながら、自然に発話の幅を広げられます - 目的のあるコミュニケーション活動
「お店屋さんごっこ」のように、学んだフレーズを実際にやりとりに使う場を設定。知識としての英語が、“使える道具”へと変わります
この時期は、「英語って役に立つ!」という実感を与えることが、次の学びへ進む推進力になります
小学5~6年生:一生の学びの土台を作る時期
高学年になると、子どもたちは抽象的な思考もできるようになり、聞く・話す・読む・書くの4技能を統合して学ぶ段階に入ります。
ここでの目標は、自律的に学び続けられる力を育てることです
- 多読
辞書を使わず、自分のレベルに合った少しやさしい本をたくさん読む活動です
続けることで語彙が増え、読むスピードもアップ。日本語に訳さずに英語を理解する「英語脳」の土台が作れます。レベル別の「Graded Readers」が便利です - 多聴
やさしい英語をたくさん聞くことで、リスニング力を強化します - 具体例から自然に学ぶ文法
文法を直接教えるのではなく、いくつかの例文を観察して自分で規則性を見つける方法です。「発見する体験」があることで、記憶にしっかり定着します - 段階を踏んで身につけるライティング力
まずは書き写しから始め、モデル文を使った作文、そして目的のある短い文章へと段階的に進めます
この時期に身につけた力は、中学以降の学びだけでなく、生涯にわたる英語学習の土台となります
家庭環境が学びに大きな影響を与える
小学校での週1~2時間の英語の授業だけでは、言語を身につけるのは難しいものです
そのため、家庭環境が英語学習の成否を大きく左右します
保護者の役割は「教師」ではなく、子どものやる気を引き出すサポーター
保護者の英語力は関係ない
研究によれば、子どもの英語力と保護者の英語力には強い関連はありません
大切なのは、関わり方と前向きな姿勢です
完璧な英語を話すことよりも、「一緒に学ぶ仲間」として関わることが、子どもにとって何倍も価値があります
すぐに試せる家庭での工夫
- 学習者としてのロールモデルを示す
保護者自身が英語を楽しむ姿は、子どもにとって動機づけになります - 子どもの「好き」を学習のエンジンにする
恐竜やアニメ、スポーツなど、子どもが夢中になっているテーマを英語学習に結びつけると、自然にやる気が高まります - 心が落ち着く接し方
結果よりもプロセスを褒め、小さな成功を一緒に喜ぶことで、子どもは「自分でもできる!」と感じます
間違いを恐れず挑戦できる環境を作ることが、何よりも大切です
小学生英語学習のまとめと実践ポイント
小学生の英語学習は、発達段階に合わせた段階的なプロセスが理想です
- 低学年:英語を「好き」と感じる
- 中学年:「使ってみたい」という意欲を育てる
- 高学年:自律的に「使いこなす」力を身につける
この順番で進めることで、無理なく自然に英語力が伸びていきます
- インプットを最優先する
言語習得のエンジンは、理解できる「聞く・読む」のインプットです - ポジティブな心理状態が学習効率を高める
不安や緊張が少なく、好奇心や興味が高い状態は、脳の吸収力を最大化します - 暗黙知から形式知へ
まずは体験を通じて自然に習得し、その後で文法や規則性に気づくことで、記憶が深く定着します - 集中よりも継続
毎日少しずつ、楽しく英語に触れる習慣こそが、長期的な成功のカギです
子どもが楽しく学べるように、科学的に裏付けられた方法と、心に寄り添う温かさの両方を大切にしてあげたいですね
学年ごとのおすすめ活動とポイント
| 学年 | 基本原則 | 主な焦点 | 主な活動 | 大人の役割 | |
| 低学年 (1-2年生) | 楽しい没入体験 | 音声インプット、ポジティブな情動形成 | 英語の歌、チャンツ、手遊び | 絵本の読み聞かせ | TPR(全身反応教授法)体の動きを使って学ぶ |
| 中学年 (3-4年生) | 意味のあるコミュニケーション | 音声と文字の接続、チャンクによる発話、自己効力感の育成 | 体系的なフォニックス学習 | チャンクを用いたロールプレイやゲーム | 目的のあるペアワークやグループ活動 |
| 高学年 (5-6年生) | 自律的な技能統合 | 4技能の統合、読解・聴解の自動化、言語への気づき | 多読(Graded Readers) | 多聴(音声付き教材) | 気づきを促す帰納的な文法活動 段階的なライティング練習 |